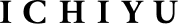ダウンライトの魔術師、爆誕。
どうも、ややイケメンです。
いやぁ、また言われちゃいました。
建築ザムライさんから、「ダウンライトの魔術師」って。
・・・魔術は使ってません。笑
どっちかというと、ただ光の角度と距離と雰囲気で戦ってるだけなんですけどね。
でも確かに、照明ってうまく使うと魔法みたいに空間が変わるんです。
同じ部屋でも、光の落とし方ひとつで「え、これ同じ家!?」ってくらい表情が違う。
今日はそんな“魔術師”の正体、つまり上質空間をつくる照明の極意5つを、
笑い少々、真面目多めでお話ししていきます。
ルール1:「空間」じゃなくて「目的」を照らす
まず最初の魔法はこれ。
“なんとなく明るくする”のをやめること。
「ここを照らしたい!」っていう“目的”を決めるんです。
たとえば、
- ダイニング=家族が顔を見ながらご飯を食べる場所
- ソファ前=くつろぐ場所
- 廊下=歩くための道
明るさを「均一」にしちゃうと、空間がのっぺりして落ち着かない。
でも“人が何をするか”を基準に光を置くと、
自然と陰影が生まれて、奥行きが出るんです。
要は、「照明=演出家」。
家を明るくするんじゃなくて、暮らしを照らすんです。
ルール2:ダウンライトの“使い分け”が大事
ダウンライトって、
直径100φの大きいやつと、50φのちっちゃいやつがあるんですよ。
これ、見た目の問題じゃなくて、照らす範囲と雰囲気が全然違う。
たとえば、
- ソファの後ろ:100φでふわっと明るく。
- キッチンのカウンター:50φでピンポイントに照らす。
100φをカウンターに使っちゃうと、光が広がりすぎて料理が“発光”しちゃいます。笑
逆に50φをリビングに使うと、座った時に「え、ここ洞窟?」みたいに暗い。
つまり、光にも役割がある。
「どこに・どんな光を落とすか」っていう引き算が大事なんです。

ルール3:眩しさを消す
ダウンライトって、直接見ると「うわっ、眩しっ!」ってなるじゃないですか。
あれ、完全にNG。
照明は“見るもの”じゃなくて、“照らされたものを感じる”もの。
だから、僕の家ではLDKの天井に直接光が当たる場所はありません。
全部、壁や天井を反射させて“間接的に”照らしてる。
これをやると、空間が一気に柔らかくなる。
「目に優しい=心に優しい」です。
ちなみに僕の中では、
「眩しさを消す=上質への第一歩」っていう法則がある。
つまり――
光を“消す”ことで、暮らしが整う。
これが、魔法です。(笑)
ルール4:色で使い分ける
白い光=会社
オレンジの光=家
これ、僕の中での考えです。笑
白い光はスイッチが入るんですよ。
「よし、仕事しよう!」っていうあの感じ。
逆にオレンジは、脳が「休める」って錯覚する。
だから僕の家は、白色ゼロ。全部オレンジ。
夜に電気つけた瞬間から、心が“オフモード”になる。
「家では戦わない」っていう考え方、大事ですよ。
家は癒しの場所。照明も“戦闘モード”じゃなくていい。

ルール5:最後は感覚。数字じゃなくて“気持ち”で整える。
照明計画って、実は最後は“感覚”なんです。
「この位置がいい」とか、「この角度、気持ちいいな」とか。
でもその感覚は、経験と根拠の積み重ねでできてる。
つまり、感覚には裏付けがある。
だから「自分で考えたいけど不安」って人は、
ちゃんとその感覚を持ってる人(=その道のプロ)に相談するのが早いです。笑
「この位置にペンダントつけたい」
「この壁を照らしたい」
そんな感覚を伝えても、相手がそれを“形”にできなければ意味がない。
良い照明計画は、ヒアリングして、プロと話をして決めていくことが大切です。
光は、家を整える。
明るさじゃない。
“陰影”こそが上質。
照明って、数字やルーメンよりも「気持ち」で決まるんですよ。
光の落ち方ひとつで、空気が変わる。
家族の時間も、気持ちのスイッチも変わる。
だから僕は、照明計画を「家づくりの仕上げ」じゃなくて、
「暮らしのデザイン」だと思っています。
家を建てる=箱をつくることじゃなくて、
光をどう使って“気持ちを整えるか”。
そこにこそ、豊かさがあると思うんです。

まとめ:あなたの家にも照明でワンランク上の暮らしを
というわけで今回は、
「ダウンライトの魔術師」が語る、上質空間をつくる5つの魔法でした。
光って、数字でもお金でもなく、感覚と暮らしで決まる。
家づくりの最後に、少しだけ“光の魔法”を意識してもらえたら嬉しいです。
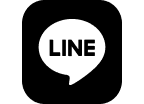
山梨県は富士河口湖町のアンティークスタイルで新築した注文住宅のルームツアー動画がややイケメンのメインチャンネルにアップされてます。動画終盤ではオーナーさんとの対談もあり、リアルな声も入っているのでお楽しみに!